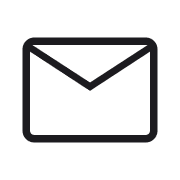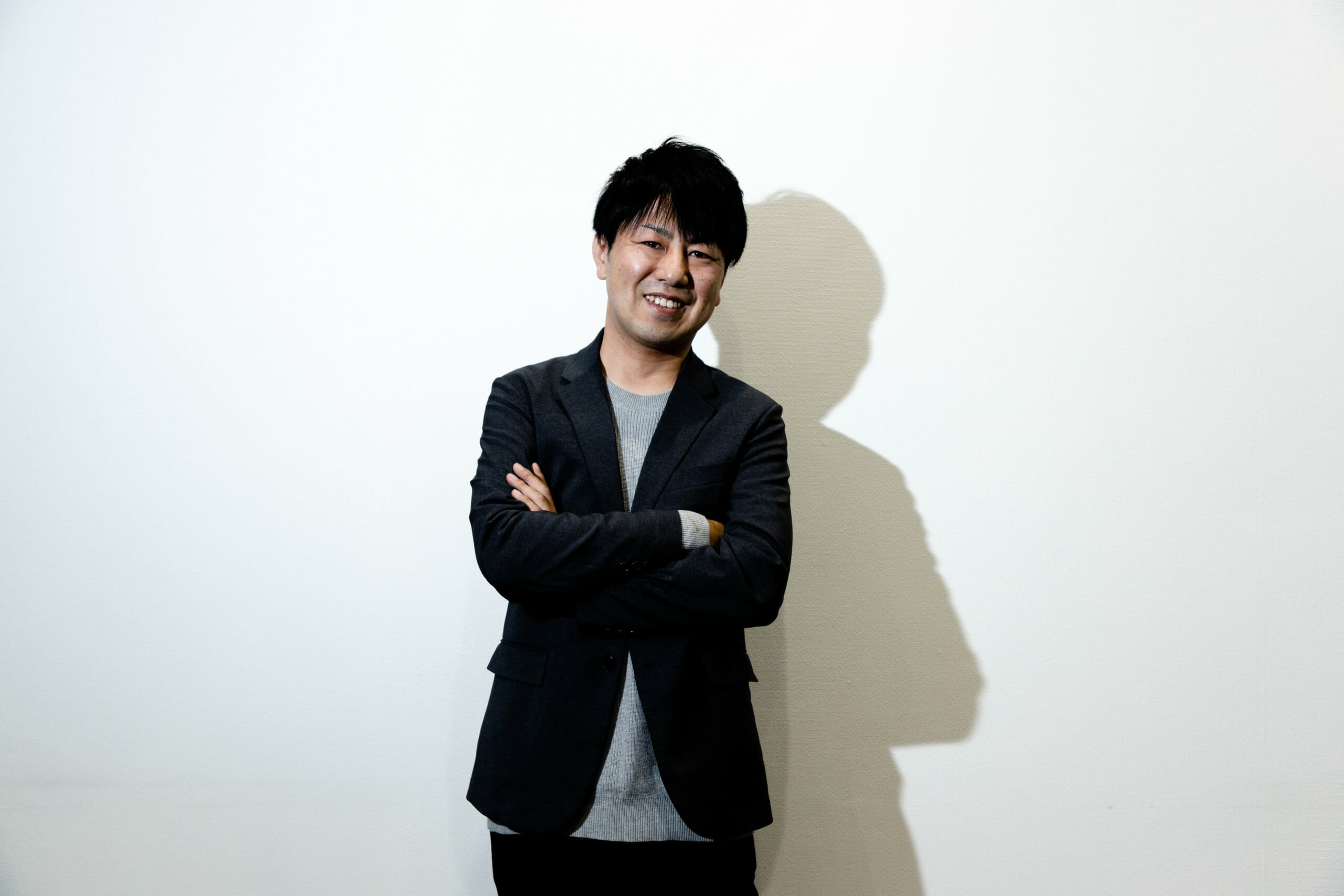WEBサイトのセキュリティ対策はどこまで対応した方が良いのか?
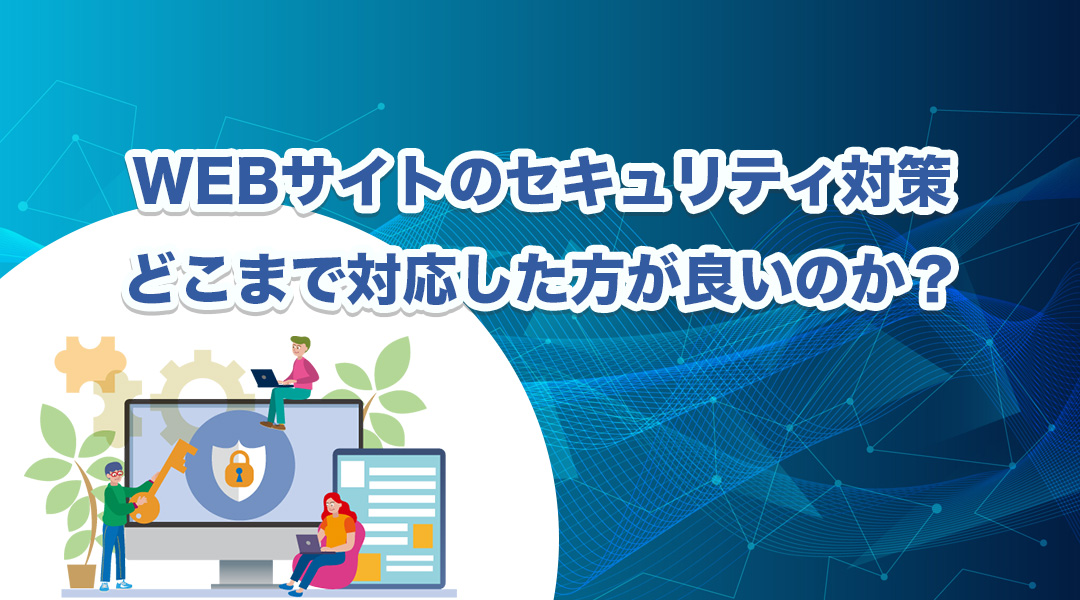
WEBサイトを運営するうえで欠かせないのが「セキュリティ対策」です。もし不正サクセスや情報漏洩が起きてしまえば、ユーザーの信頼を失うだけでなく、運用にも大きな負担がかかります。
近年、インターネット上のトラブルは年々増えており、個人情報が流出したニュースを耳にしたことがある方も多いでしょう。このような事態になる前にセキュリティ対策を施したいものですが、どこまで対策すれば安心なのでしょうか?
本記事では、WEBサイトのセキュリティ対策について詳しく解説していきます。
WEBサイトのセキュリティ対策にはどんなものがある?

WEBサイトの安全性を高めるためには、どのようなセキュリティ対策があるのでしょうか。
以下では「WAF」「脆弱性診断」「常時SSL化」の3つを取り上げ、それぞれ分かりやすく解説していきます。
WAFを導入する
WAF(Web Application Firewall)は、WEBサイトへのアクセスを監視して、攻撃性のある通信を遮断するセキュリティ対策です。通常のファイアウォールでは防ぎきれない、SQLインジェクションやクロスサイトスクリプティングなどの攻撃を遮断し、サイトの改ざんや情報漏洩といった重大な被害を未然に防ぐことができます。
WAFには、クラウド型・アプライアンス型・ソフトウェア型などがあり、運営するサイトの規模やコストに応じて選択可能です。ただし、WAFだけに頼るのではなく、基本的なセキュリティ対策やプログラムの修正と組み合わせることで、より高い効果を発揮します。
定期的に脆弱性診断を実施する
脆弱性診断とは、WEBサイトやシステムに潜んでいる弱点を洗い出す取り組みです。診断を行うことで、外部からの攻撃に悪用される恐れがある箇所を早期に発見でき、被害を防止するための改善策を取ることが可能になります。
診断の方法としては、自動化されたツールによる診断と、セキュリティの専門家が実際の攻撃を想定して行う手動での診断があります。
Webサイトは更新や機能追加によって新たな脆弱性が生まれるため、一度だけでなく定期的に診断を実施することが欠かせません。定期的に診断を行うことで、利用者が安心してサービスを利用できる環境を維持できます。
WEBサイトを常時SSL化する
常時SSL化とは、WEBサイトのすべてのページを「https」で運用し、通信を暗号化する仕組みです。これにより、ログイン情報や問い合わせフォームだけでなく、通常の閲覧ページでも通信が保護され、不正アクセスのリスクを大幅に減らすことができます。
Googleなどの検索エンジンは、SSL化されたサイトを優先的に評価する傾向があるため、セキュリティ面だけでなく、SEO効果も期待できます。主要ブラウザは非SSLサイトに「安全ではない」という警告を表示するため、ユーザーの離脱防止にも繋がります。現在では常時SSL化は特別な対策ではなく、WEBサイト運営においては基本的な対策となっています。
WEBサイトのセキュリティ対策する際に押さえておきたいポイント

WEBサイトを守るためには「インフラ」「フロントエンド」「CMS」などの各層において、基本的なセキュリティ対策を押さえておくことが大切です。それぞれの役割を整理し、詳しく解説していきます。
インフラ
インフラはWEBサイトの基盤であり、最初に整えるべきセキュリティ領域です。ここに脆弱性があると他の対策をしていても効果が薄れてしまいます。
まず導入すべきは、外部からの攻撃を防ぐWAFで、不正なリクエストやDDoS攻撃を遮断します。また、CDNを利用することでアクセスを分散させ、過剰な負荷によるサービス停止を防ぐことも有効です。さらに、OSやミドルウェアは常にアップデートを行い、既存の脆弱性を突かれないようにしましょう。不必要なサービスは停止し、ユーザー権限も「必要最小限」に抑えることが大切です。
フロントエンド
フロントエンドはユーザーが直接操作する領域であり、攻撃者の標的にもなりやすい部分です。代表的なリスクは、XSS(クロスサイトスクリプティング)で、情報漏洩や改ざん、乗っ取り、不正リダイレクトに繋がる可能性があります。これを防ぐためには、入力されたデータを適切にサニタイズし、CSP(Content Security Policy)を設定して不審なスクリプトを実行させないことが大切です。
外部のJavaScriptやCSSは信頼できるソースから取得し、不要なライブラリは極力使用しないことが望ましいです。フレームワークやライブラリは、古いバージョンを使い続けると脆弱性を突かれる原因となりますので、最新状態を保つようにしましょう。
CMS
CMSはサイト運営を効率化できる便利な仕組みですが、その利便性ゆえに攻撃者から狙われやすい対象でもあります。まずは、自社のセキュリティ基準を満たすCMSを選定しましょう。導入後は、CMS本体やプラグインを常に最新版に更新し、脆弱性を放置しないよう注意しましょう。また、プラグインやテーマも最新に保ち、不必要なものは削除することでリスクを抑えた運用が実現します。
管理画面のアクセス制限も重要です。強力なパスワード設定や2段階認証、役割に応じた権限管理によって不正アクセスを防ぎましょう。また、定期的にバックアップを取得することで、万一の改ざんや障害発生時でも迅速に復旧できます。
WEBサイトのセキュリティチェックの方法

WEBサイトのセキュリティを守るには、定期的なチェックが欠かせません。特に「脆弱性診断」「ペネトレーションテスト」「HTTPセキュリティ設定の確認」の3つは、基本的な対策でありながら効果的な方法です。
脆弱性診断の実施
脆弱性診断は、WEBサイトやサーバーに潜む弱点を自動で見つられるチェック方法です。脆弱性診断ツールを使うと、ソフトのバージョンが古い・パッチが未適用・設定に不備があるなど問題点を検出してくれます。診断は自動スキャンで行われるため、短時間で幅広い項目を確認でき、運用中のシステムに大きな負担をかけません。
代表的な手法に「DAST(動的診断)」があり、実際の利用と同じようにリクエストを送って挙動を調べ、攻撃の入口になりそうなポイントを洗い出します。
自動診断はコストを抑えつつ定期的に繰り返せるのが利点で、セキュリティ対策の最初のステップとして多くの企業が取り入れています。
ペネトレーションテストの実施
ペネトレーションテスト(ペンテスト)は、セキュリティの専門家が実際に攻撃者になりきってサイトに侵入できるか試す方法です。単に脆弱性があるかどうか確認するだけでなく、「もし攻撃されたらどこまで影響が広がるのか」を検証できる点が大きな特徴です。
診断は手動で行い、業務の仕組みに依存する脆弱性や設定ミスなど、機械では見つけにくい問題を明らかにします。診断時には、情報を全く渡さない「ブラックボックス」、一部の情報を渡す「グレイボックス」、全てを開示する「ホワイトボックス」といった種類があり、目的やリスクに応じて選びます。
ペンテストはセキュリティ体制を実践的に確認できるため、重要なサービスを運営する企業では特に実施が推奨されます。
HTTPセキュリティ設定のチェック
HTTPセキュリティ設定は、ユーザーとブラウザ間の通信や挙動に安全ルールを強制する効果的な手段です。代表的なものとしては、通信を強制的にHTTPSにする「HSTS」、悪意のあるスクリプトの実行を防ぐ「CSP」、クリックジャッキング対策の「X-Frame-Options」などが挙げられます。
比較的設定が容易でありながら、クロスサイトスクリプティングやクリックジャッキングといった深刻な攻撃リスクを着実に減らすことができるため、必ずチェックしておきたいポイントです。
まとめ
今回は、WEBサイトのセキュリティ対策について解説してきました。
WEBサイトを安全に運営するには、多層的なセキュリティ対策が欠かせません。代表的な方法としては、WAFによる攻撃の遮断や定期的な脆弱性診断、常時SSL化による通信の暗号化などが挙げられます。
サイトのセキュリティを維持するには、脆弱性診断やペネトレーションテスト、HTTPセキュリティ設定の確認といった定期的なチェックを行うことが効果的です。