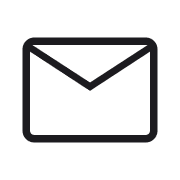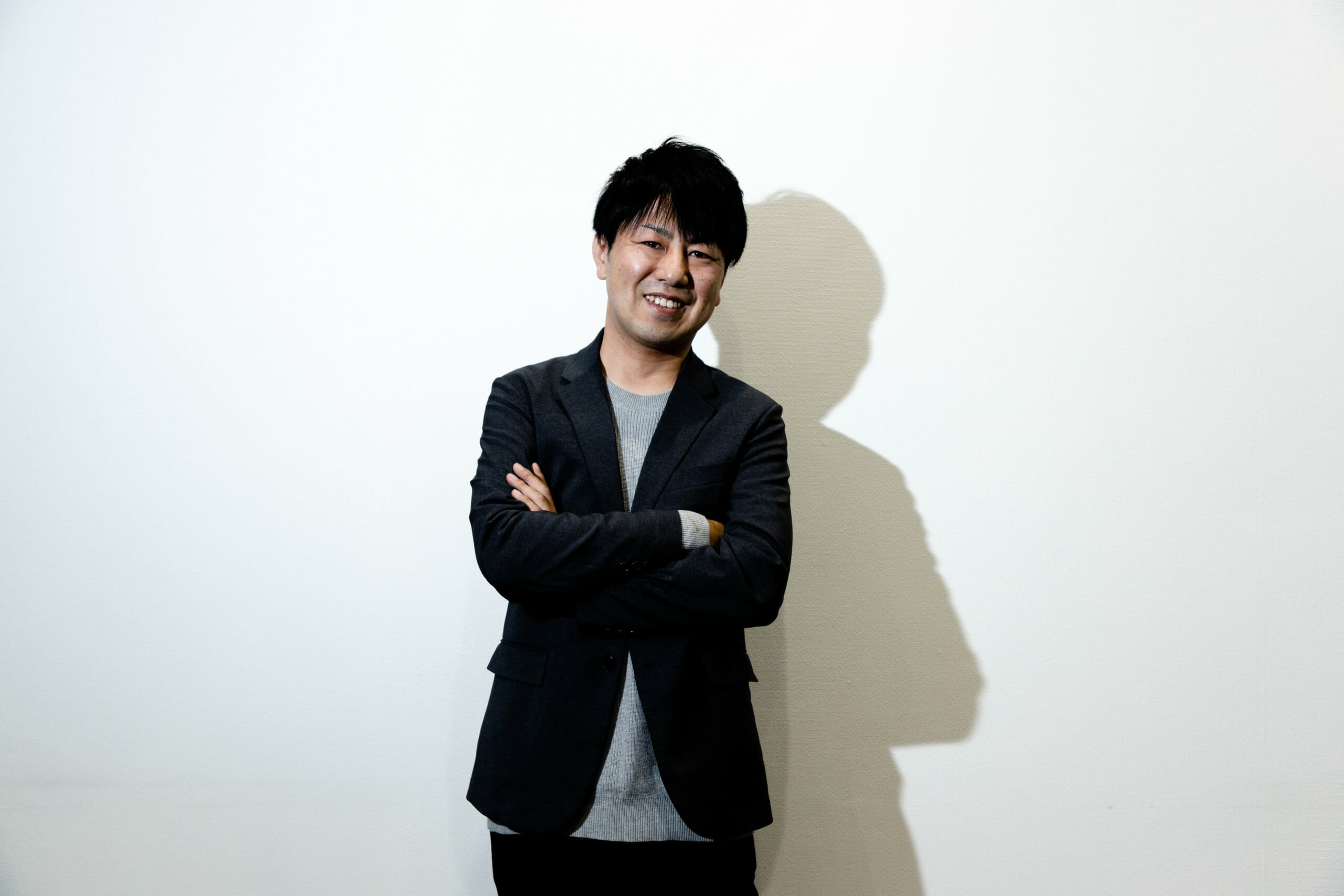ホームページ作成における画像の著作権上の注意点について
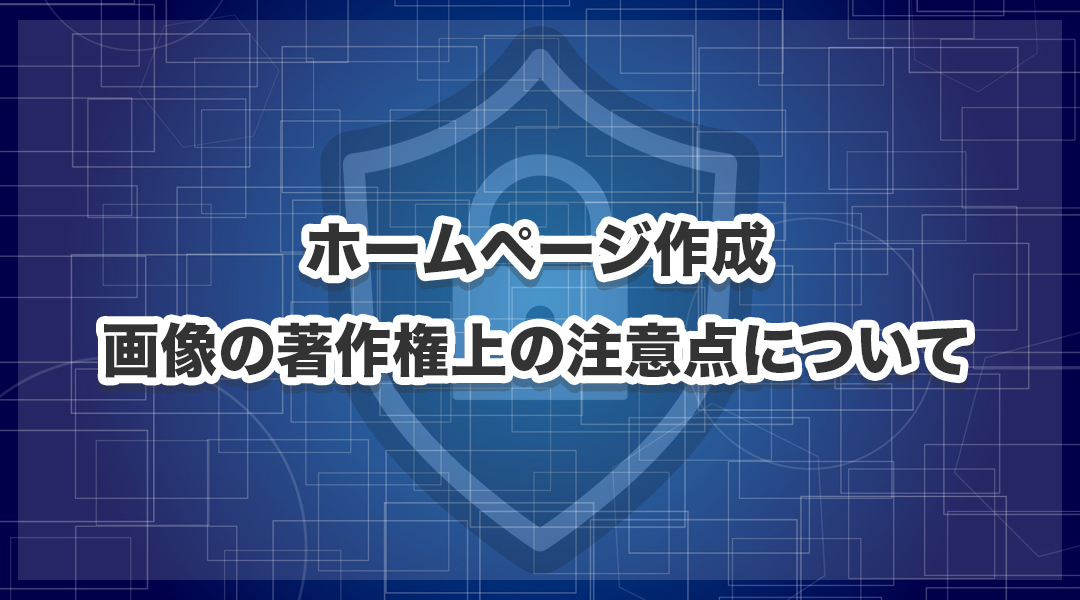
ホームページは、文字だけでなく画像を活用することで、ユーザーに強い印象を与えることができます。そのため、魅力的な画像を用いてホームページを作成したいものですが、その画像が著作権を侵害していないかどうかを慎重に確認しなければいけません。
インターネット上で見つけた写真やイラストをそのまま使うと、知らないうちに法律違反になってしまうケースもあります。では、安心して画像を利用するには、どのような点に注意すれば良いのでしょうか?
本記事では、ホームページ作成における画像の著作権について詳しく解説していきます。
そもそも著作権とは?
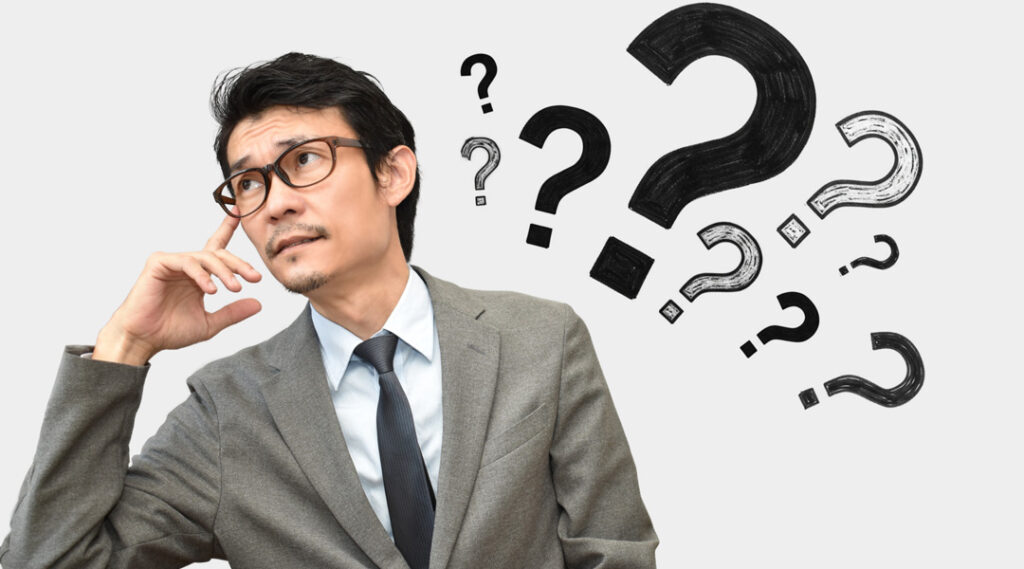
著作権とは、文章・画像・音楽・プログラムなど「思想や感情を創作的に表現したもの(著作物)」を守るために、創作者に与えられる権利のことです。著作物は完成した瞬間から自動的に保護され、登録や申請の手続きは必要ありません。
著作権には大きく二つの側面があり、作者の人格を守る「著作者人格権」と、利用方法を管理できる「著作財産権」が存在します。具体的には、複製権・公衆送信権・翻訳権などが含まれ、創作者が自分の作品をどのように使うかをコントロールできる仕組みです。
保護期間は原則として著作者の死後70年までとされており、その後は誰でも自由に利用できるパブリックドメインとなります。著作権は、無断利用を防ぐと同時に創作者の努力を正当に評価し、文化や表現活動の発展を支える役割を担っています。
ホームページ作成で著作権に該当するものについて

ホームページを作成するときは、画像・動画・文章・音楽など多様なコンテンツが利用されます。これらは著作権の対象となることが多く、適切な扱いを知らないと著作権侵害に発展する可能性もあります。
画像 / 動画
ホームページに使用する写真やイラストといった画像には、制作者の独自の表現が含まれており、著作権法によって保護されています。これは、グラフィックデザイン・イラスト・写真など幅広いものが対象で、インターネット上に公開されている画像を無断で使うと著作権侵害にあたるケースが多いです。
動画についても映像自体はもちろん、BGMやナレーション、編集構成など複数の要素に権利が関わっています。そのため、素材を使用する際には「利用に許可が必要か」「フリー素材ではないのか」を必ず確認する必要があります。
文章
ホームページに掲載する文章、サービス紹介・商品説明・ブログ記事などには、製作者ならではの工夫や表現が含まれており、創作性が認められれば著作権の保護対象となります。逆に、単純な事実やオリジナリティの低いキャッチコピー・スローガンなどは、創作性が不足していると判断される場合もあります。
文章を引用する際は、出典の明記や引用部分の明確化など、著作権法に定められたルールを守ることが大切です。
音楽
ホームページ内で流れるBGM・効果音・歌詞付きの楽曲なども著作権の対象です。音楽は短いフレーズや効果音であっても、創作性が認められれば保護されることがあるため、各音楽サイトに配信されている楽曲やインターネットで見つけた音源を無断で使うのは非常に危険です。
使用する際は、著作権フリー音源を利用するか、JASRACなどの管理団体や制作者から許可を得る必要があります。
ホームページ作成で注意したい著作権に関する事項

ホームページ制作では、画像・文章・動画などの無断利用によって、著作権侵害になることがあります。ここでは、具体的な侵害例とその罰則について解説していきます。
著作権侵害にあたる例
ホームページ制作でよくある著作権侵害の例としては、画像・文章・動画を制作者の許可なく使用してしまったケースが多いです。例えば、SNSや他サイトで見つけた写真やイラストを無断で掲載したり、他人の記事をコピーして掲載する行為は著作権侵害にあたります。また、YouTubeなどの動画を許可なく埋め込んだり、BGMとして使用することも同様です。
「短いから大丈夫」「一部分なら問題ない」という考えは大変危険です。
著作権侵害の罰則
著作権侵害には民事上と刑事上の両方で厳しい処罰が設けられています。刑事罰としては、故意の侵害に対して「10年以下の懲役」または「1,000万円以下の罰金」、もしくはその両方が科される可能性があります。企業などの法人の場合はさらに重く、最大「3億円以下の罰金」となる場合もあります。
民事上では、著作権者から差止請求や損害賠償、謝罪広告などを求められるケースがあります。これらは金銭的負担だけでなく、信用を失う大きなリスクとなるでしょう。
著作権トラブルを回避するポイントとは?

ホームページ制作では、著作権トラブルを避けるための工夫が必要になります。CMSやフリー素材、契約による権利の明確化など、適切な対策を理解しておくことで、安心してサイトを運営できます。
CMSを利用する
CMS(WordPressやShopifyなど)を使うと、テンプレートや機能追加用のプラグインが公式に提供されており、ライセンスも明確に示されているため、著作権を侵害する危険を減らすことができます。加えて、定期的なアップデートによってセキュリティ面も強化されるため、安心して利用することができます。
CMSによっては、不正な外部コンテンツを排除してくれる仕組みもあるため、安心してホームページを構築できる環境が整っています。
著作権譲渡契約を締結する
外部の制作会社やフリーランスにホームページを依頼した場合、著作権は原則として制作者に帰属します。そこで重要なのが「著作権譲渡契約」を結ぶことです。この契約を交わしておくことで、納品後に作成した文章や画像の権利が依頼者に移り、自由に修正・変更ができるようになります。
契約をしていなければ、公開後に「勝手に変更できない」「別の用途に使えない」といった制限が発生する可能性もあります。後のトラブルを防ぐためにも、契約段階で権利の帰属をしっかり明記しておくことが大切です。
フリー素材を活用する
ホームページに使う画像や動画すべてを自分で用意するのは大変なので、フリー素材を活用するととても便利です。ただし、「フリー素材=自由に使える」と思い込むのは危険です。フリー素材を提供するサイトの中には「商用利用不可」や「クレジット表記が必要」などの使用条件がある場合があります。
利用前には必ず提供元の利用規約を確認し、必要なら出典や制作者名を明記することで、安全に素材を使うことができます。
コピーライトの書き方について

コピーライト(Copyright)とは、著作物に対する権利を主張する表記のことを指します。例えば「© 2025 Usagi Inc.」のように、©マーク・発行年・権利者名を組み合わせて表記することで、自分がそのコンテンツの著作者であることを明確に示します。
著作権は作品の創作性と同時に自動的に発生するため、表記がないからといって権利は消えません。コピーライト表記があることで、サイト利用者に対して「このサイトには著作権がある」という警告になり、法的リスクを避けるための抑止力として働きます。
一般的なコピーライトの書き方としては、まず「©」または「Copyright」の表記、続いて、発行年と著作権者の名前(例:© 2025 abc company.)、そして「All rights reserved」などの全ての権利を保有していることの明記になります。これらの要素をまとめて「© 2025 abc company. All rights reserved.」のように記載します。
まとめ
ホームページ制作において、著作権は注意すべきポイントです。文章・画像・動画・音楽などは、創作性があれば著作権で保護されるため、無断で使用すると著作権侵害にあたります。侵害した場合は民事上の損害賠償や刑事罰など厳しい処分を受ける可能性があります。
著作権侵害を避けるためには、CMSを活用して権利関係の明確な素材を利用することや、制作を依頼する際に著作権譲渡契約を結ぶことが効果的です。また、フリー素材を利用する際も利用規約を必ず確認し、適切に使用することが求められます。