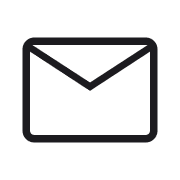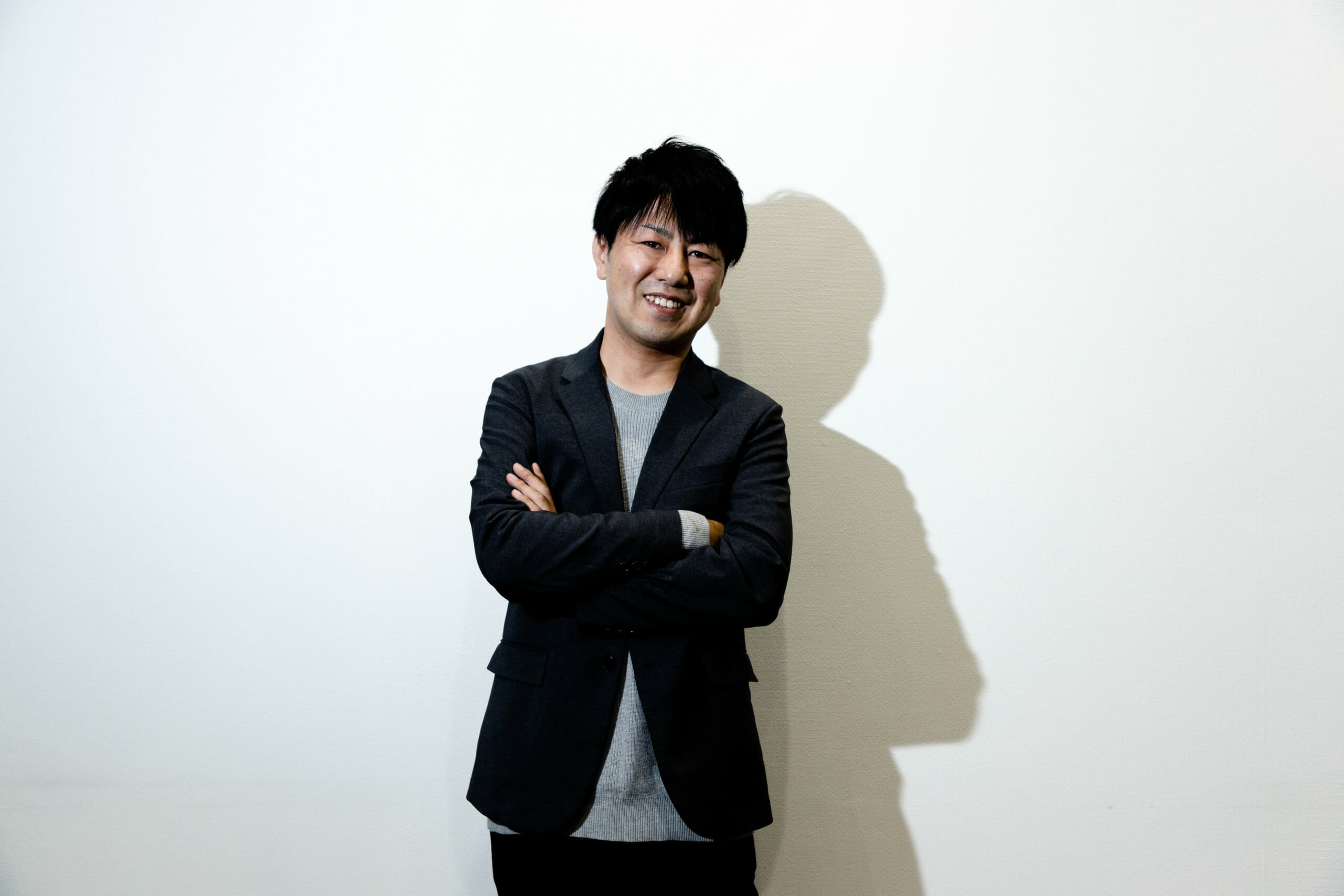WEBサイトの構成の基本的な考え方と階層構造について
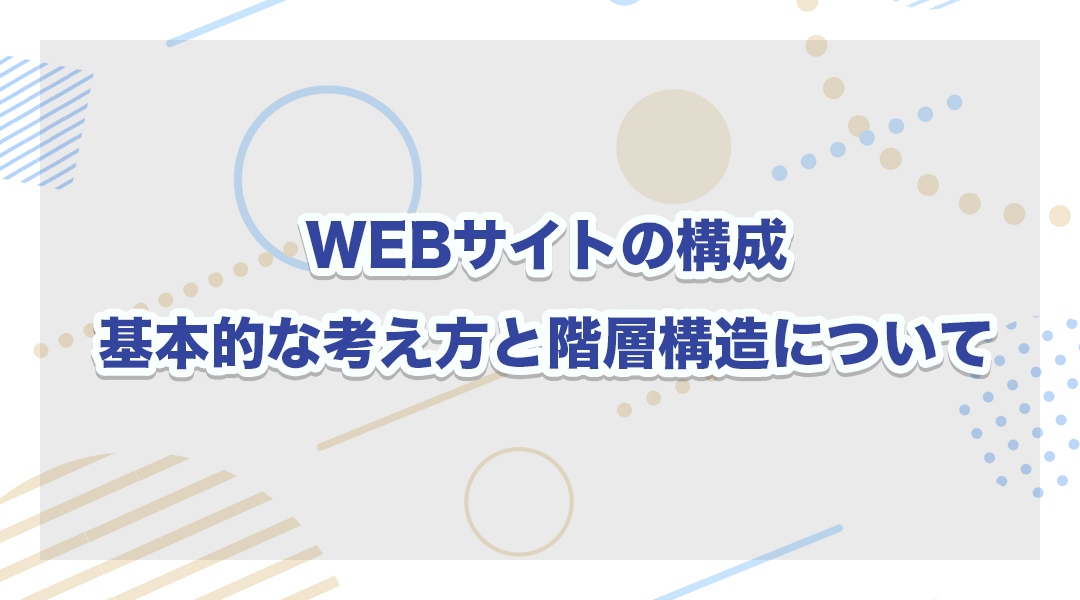
自社の情報を伝えるために作られるWebサイトですが、単にページを並べるだけではユーザーにとって使いやすいものにはなりません。どのようにページを配置し、どの順序でアクセスできようにするかといった「構成」と「階層」の工夫が、ユーザー体験の向上に繋がります。
しかし、具体的にどのような考え方で構成を整えればよいのか、また階層をどう組み立てれば分かりやすいサイトになるのか、詳細まで理解している人は多くありません。
そこで本記事では、WEBサイトの構成と階層構造について詳しく解説していきます。
そもそもWEBサイトの構成とは?

WEBサイトの構成とは、サイトの中にあるページをどのように整理し、どう繋げていくかを考える仕組みのことです。簡単なイメージとしては、訪問者が迷わず情報を見つけられるようにする「設計図」のような役割を持っています。
ページを階層ごとに分けたり、サイトマップを作ったり、内部リンクを工夫したりすることで、ユーザーにとっても検索エンジンにとっても分かりやすいサイトになります。
こうした基本を押さえておくことで、コンテンツを効果的に配置することができるようになります。
WEBサイトの構成の基本的な考え方
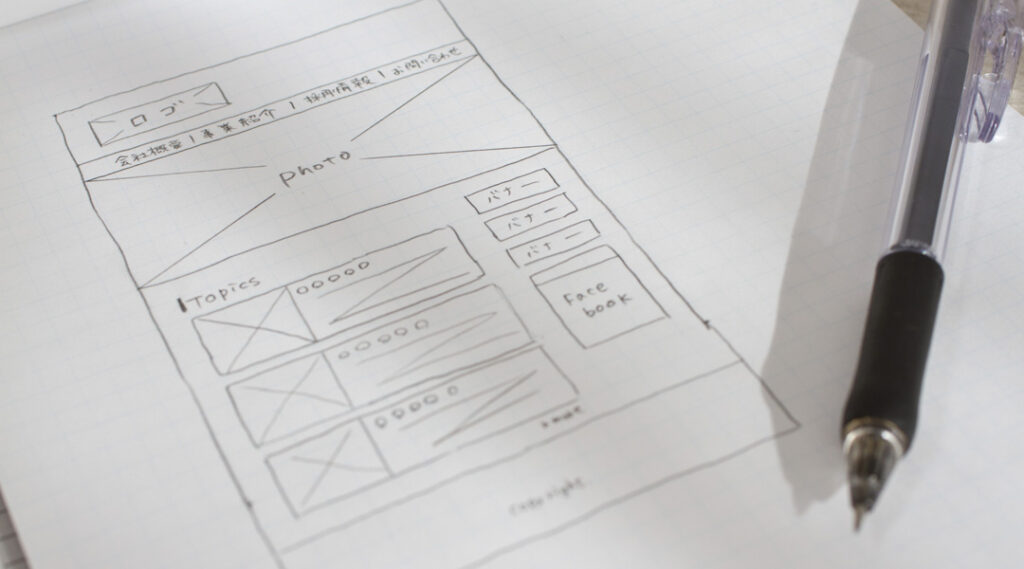
WEBサイトを設計する際には、「サイトマップ」と「ワイヤーフレーム」の2つについて考える必要があります。
サイトマップは、サイト全体のページ構成を階層的に示す「設計図」のようなもので、ユーザーや検索エンジンが目的のページにたどり着く道筋を明確にします。WEBサイト全体の構成をまとめるには、トップページから目的のページへどう遷移するかを決めていくのが大切です。
一方、ワイヤーフレームは、ページごとのレイアウトを視覚化した「骨組み図」のようなものです。色や装飾を省いた状態で、見出し・本文・画像・ボタンなどの配置や機能を考えていきます。ワイヤーフレームを作成することで、ユーザーの操作性やデザインの方向性を早期に確認することができます。
WEBサイトの構成を考えるメリットとは?

WEBサイトの構成を考えるには、訪れる人が求める情報をすぐ見つけられるようにしたり、検索エンジンが正しく内容を理解・評価しやすくしたりするために重要です。
以下では、WEBサイトの構成を考えるメリットについて解説します。
ユーザーが必要な情報にスムーズにアクセスできる
サイトの構成がしっかりとしていると、ユーザーは迷うことなく目的のページにたどり着けます。逆に、情報が散らばっていたり階層が複雑すぎたりすると、ユーザーは途中で離脱してしまう可能性が高まります。
直感的に分かるナビゲーションや明確なカテゴリ分けを意識することで、ユーザーは「ここに答えがありそうだ」と直感で判断できます。こうした工夫がサイトの使いやすさを高め、結果として滞在時間や回遊率も伸びやすくなります。
検索エンジンのクロール効率が改善される
検索エンジンは、サイトの中をクローラーが回ってページを読み取ります。サイトの構成が整理されていると、クローラーが効率的に情報を収集でき、ページを正確にインデックスしてもらえます。特に、トップページから3クリック以内でアクセスできるような階層にすると、SEO対策にも効果的です。さらに、パンくずリストや内部リンクを設置することで、検索エンジンだけでなくユーザーにとっても便利な道しるべになります。
サイトの方向性を明確に決めることができる
サイトの構成を考えておくと「このサイトは何を伝える場所なのか」ということがはっきりします。例えば、商品紹介をしたいのか、情報発信をしたいのかによってページの作り方は変わります。あらかじめページの方向性を決めておくことで、サイトに一貫性が出て、ユーザーが内容を理解しやすくなります。さらに、運営側にとっても方向性がブレにくくなるため、長期的な戦略や改善施策を立てやすくなるのです。
WEBサイトの階層構造について

WEBサイトの階層構造とは、サイト内のページを分類し整理するための基本的な設計方法です。トップページからカテゴリページ、コンテンツページへと繋がっていき、ツリーのような形のフォルダ構造になります。このように設計された階層構造は「ディレクトリ構造」とも言われています。
こうした構造は、ユーザーにとって目的の情報へたどり着くまでの道のりが明確になるため、ユーザー体験が向上します。また、検索エンジンのクローラーも効率的にサイトを巡回できるようになるため、重要なページを見つけやすくなりSEOにも効果的です。
整理された階層構造は運営側にとっても管理しやすく、将来的なページの追加・修正をスムーズに行えるという利点があります。
WEBサイトの構成(サイトマップ)の作成手順について

WEBサイトを制作する際は、サイトマップの作成が欠かせません。サイトマップは、サイト内のページを整理し、ユーザーと検索エンジンの双方に分かりやすい構造を提供します。以下では、効果的なサイトマップを作成する手順をご紹介します。
サイトマップ作成の第一歩は、WEBサイト作成の目的を明確にすることです。製品やサービスの売上向上を目的とするのか、情報提供やブランド認知度の向上を目指すのか、目的によってサイトの構成や必要なページが大きく変わります。
目的が不明確だと、ページの内容や順序がばらばらになり、ユーザーにとって使いにくいサイトになってしまいます。そのため、サイトマップを作成する前に、サイトの目的やターゲットユーザーをしっかりと決めておく必要があります。
サイトの目的が決まったら、必要なページをリスト化して洗い出しましょう。例えば、企業サイトであれば「会社概要」「サービス紹介」「お問い合わせ」「ブログ」「採用情報」など、多角的な情報を網羅することが大切です。
ページを洗い出す際は、ユーザーが求める情報や目的に沿ったコンテンツを中心に考えて、整理していきます。この作業によって、後でページを分類したり階層化したりする際にスムーズに進めることができます。
続いては、洗い出したページを関連性のあるカテゴリごとに整理します。例えば「会社情報」「サービス」「採用情報」「お知らせ」といったカテゴリを作り、それぞれに関連するページを繋げていくイメージです。この分類作業によって、サイト全体の構造が整理され、ユーザーが目的のページにアクセスしやすくなります。検索エンジンにとってもサイトの構造が明確になり、インデックスの効率化やSEO評価の向上にも繋がります。
最後に、分類したページをもとにサイトマップを作成し、ページの階層を決めていきます。トップページを起点に、カテゴリページ・サブカテゴリページ・コンテンツページへと階層的に整理することで、ユーザーが必要とする情報に迷わずたどり着けます。これによって、クローラーもページの重要度や関係性を理解しやすくなるため、SEOにも有利になります。
WEBサイトの構成(サイトマップ)の作成で便利なツールの紹介

WEBサイトの構成を明確にするためには、サイトマップの作成が必要不可欠です。特に、XML形式のサイトマップは、検索エンジンにサイト構造を伝える重要な役割を果たします。以下では、サイトマップ作成に役立つツールをご紹介します。
XML-SiteMaps.com
XML-SiteMaps.comは、ウェブサイトのURLを入力するだけで、XML形式のサイトマップを自動生成できるオンラインツールです。特別なソフトウェアのインストールは不要で、手軽に利用できます。
生産されたサイトマップは、Googleなどの検索エンジンに提出することで、サイトのインデックス登録を効率的に進め、SEO効果を高めることが期待できます。サイトの更新頻度やページの優先度などの設定も可能で、柔軟な対応が可能です。
Microsoft Excel(エクセル)
Microsoft Excel(エクセル)は、サイトマップを構造的に整理するのに適したツールです。セルを活用して階層構造を表現することができ、カテゴリーの追加や削除も簡単に行えます。さらに、ページのURLやタイトル、メタディスクリプションなどの情報を一元管理することができ、サイト全体の構成を把握しやすくなります。
事務作業に慣れている方にとっては直感的に作成できるため、効率的な作業が可能です。
Microsoft PowerPoint(パワーポイント)
Microsoft PowerPoint(パワーポイント)は、視覚的にサイトマップを作成するのに適しています。パワーポイントに搭載されているSmartArt機能を使用することで、階層構造を簡単に表現することができます。スライド上で自由にテキストや図を配置できるため、プレゼンテーション資料としても活用できるでしょう。
特に、クライアントへの提案やチーム内での共有時に、視覚的に分かりやすいサイトマップを作成することができ、コミュニケーションが円滑に進みます。
まとめ
今回は、WEBサイトの構成と階層構造について解説してきました。
WEBサイトの構成を考える際には、サイトマップの作成が重要なポイントとなります。サイトマップは、ページの整理や階層構造を明確にし、ユーザーが目的の情報に迷わずアクセスできるだけでなく、検索エンジンの評価向上にもつながります。
サイトマップの作成には、XML-SiteMaps.comのような自動生成ツールや、一覧管理できるExcel、視覚的な階層表現などが便利なPowerPointなどがあります。それぞれの特性を活かすことで効率的かつ分かりやすいサイトマップが作成できるでしょう。